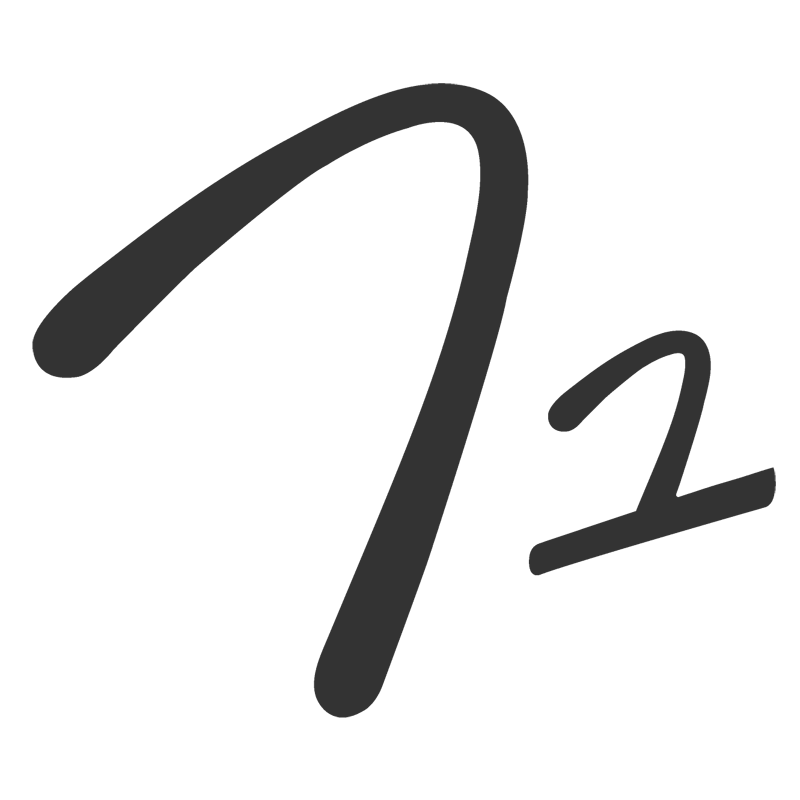先日刊行された市川哲史×藤谷千明『すべての道はV系に通ず。』が非常に面白い。<草創期の共犯者・市川>と<ゼロ年代の業人・藤谷>による異なる観視点は、お互いを保管しあう資料的意味合いは大きく。そして、あのおおらかな時代の実体験を基に感覚的に語る市川さんとクロニクル史観から現実主義を求めていく藤谷女史のやりとりは、そもそもの読み物として大変面白い。なんせ、私は市川さんの文章で音楽的素養を学んだ(こじらせた)し、外部執筆するようになったきっかけは藤谷女史の推挙があってのことだったので、そんなお二人の“素”の会話は微笑ましくもあり。大体こういう類の本は「おいおいおい」「そこは違うだろ」といった突っ込み要素や、良くも悪くも賛同しかねるところがあったりするものなのだが、この本には、7割の「そうそうそう」と3割の「あー、こういう考えもあるわけね」しかない。両名世代はもちろん、近年の若い世代のV系ファンにも必読書。
内容に関して詳しく触れるつもりはないが、ちょっと取り上げておきたいところがある。<VISUAL JAPAN SUMMIT>(2016年)での、MUCC逹瑯の「いつからヴィジュアル系はカッコ悪いとされるようになったんだろう」発言にはじまる「ヴィジュアル系<被差別>史」。この発言は私も現地で耳にし、実に逹瑯らしい発言であり、彼だからこその説得力ある言葉だと思ったし、いろいろと考えさせられることがあった。
同書ではこの発言に対し、「“ネオ・ヴィジュアル系”世代はピンと来ない」と触れらている。ごもっともだ。しかし、ヴィジュアル系がジャパニーズ・カルチャーとして海外で認知されるようになり、その地位が確立されたのはここ10年くらいの話。「でも90年代にもヴィジュアル系ブームあったじゃん」というのはその通りだが、近年の再評価から美化されている部分もあるのが現実。というより、良い部分ばかりが語り継がれてる節もある。「昔、XやLUNA SEA聴いてました」と公言することが“恥ずかしい”ことだったり、外資系CDショップはヴィジュアル系バンドのCDを置かない、というウソのような本当の時代があった。いわゆる“ヴィジュアル系黎明期”といえるオケバン(お化粧バンド)〜黒服系の直撃世代である我々70年代生まれは、好き嫌いは別として「ヴィジュアル系はカッコ悪い」という風潮を幾度となく真に感じてきたはずだ。先の逹瑯の発言を「彼だからこその説得力」と評したのは、そうした時流の渦中に居て、様々な葛藤?をリアルに乗り越えてきたヴィジュアル系ロックバンドのフロントマンだからだ。
私は<VISUAL JAPAN SUMMIT>を執筆業の“仕事”として行っており、この逹瑯の発言にも触れた文章を書くつもりでいた。しかしながら、様々な事情により、その企画自体が頓挫してしまい、筆を取ることなく自分頭の中のみので終わってしまっていたのだ。機会さえあれば触れたかったテーマでもあるので、今ここであらためて取り上げておきたい。
“ヴィジュアル系”ができた頃には既にカッコ悪かった
ヴィジュアル系が世間に広く認知されたのが90年代後半。SHAZNAを筆頭としたヴィジュアル系四天王(SHAZNA、L’acryma Christi、MALICE MIZER、FANATIC◇CRISIS)の台頭があり、これが新しいムーヴメントとして勃興していく。と、同時にその上の世代であるBUCK-TICKやXが彼らと同列に語られるようになった。音楽ではなく容姿だけで語られてしまうような語感が、どこかメディアに茶化されている気分にもなり、本人たちはさておき、憤りを感じるファンも少なくはなかった。何かと話のネタになるL’Arc〜en〜Cielの「ヴィジュアル系じゃない」発言は、化粧や容姿の問題ではなく、己の美学を追求しているだけなのに、流行の一環として後追いの言葉で括られることに対する反発であり、「よく言ってくれた」という賛の声もあったことは忘れてはならない。
90年代の日本の音楽シーンはまだまだ未発展であり、そのぶん、流行り廃りや移り変わりも激しかった。自分が歳を取ったぶん当時を思い出し、懐古主義になってしまう側面は否定はしない。ただ、ここ10年でCD売上げの変動やストリーミングサービスなどによって音楽の愉しみ方が大きく変わったとはいえど、当時を思いかえせば、レコードからCD、カセットからMD、バンドブームからタイアップ競争によるCDバブル、大型音楽フェスの開催……90年代は凄まじい時代だった思う。それは、音楽ジャンルの発展においても同等であり、それがヴィジュアル系の基軸をみると、1993年が非常に重要な年であることがわかる。
黒服系総洋楽化
「人より目立ちたい」という原点からはじまったであろうオケバン〜黒服系バンドが、それを超える飽くなき音楽探求により、自らの音楽を深化させていく様は90年代中頃に盛んに見られた。それは同時にファンでありリスナーの耳を鍛えることになった。
そのひとつの分岐点が1993年だった。この年、日本のロックシーンを大きく揺るがした問題作が数多くリリースされている。BUCK-TICK『darker than darkness -style 93 -』(6月)、Zi:KILL『ROCKET』(6月) 、hideのソロデビューシングル『EYES LOVE YOU』(8月) 、SOFT BALLET『INCUBATE』(11月)……などなど、この年を皮切りにこの界隈のバンドたちが一気に洋楽方面のインダストリアル〜ラウドロック方面に流れていった。ちなみに海外において、この畑での名盤となる、Nine Inch Nails『The Downward Spiral』やKORN『KORN』などは翌1994年のリリースであるから、これらの日本のバンドがいかに前衛的であったかがわかるはずだ。そして反面で、ザ・ブルーハーツやユニコーン、JUN SKY WALKER(S)……といったバンドブームで一時代を築いたバンドたちが時流のふるいに掛けられてしまった年でもある。(関連記事:1993 J-ROCK総洋楽化「おれたちインダストリア充」の巻 - ジェイロック回顧主義 #3)
そんな先駆者たちのおかげもあって、90年代中頃にはすっかり“洋楽耳”になってしまっていたリスナーにとって、音楽ではなく見た目だけで判断されるような“ヴィジュアル系”で括られることは、非常に納得いかなかったのだ。今の感覚では「ヴィジュアル系バンドに対して失礼」と思うかもしれないが、この時代はまだ洋楽至上主義であり、洋楽コンプレックスに支配され、“外タレ”への憧れが根強かった。用もないのに六本木のWAVEを徘徊して、とりあえず「ビョーク聴いていればオサレ」だった。だから日本のバンドを聴いてるものなら「まだそんなの聴いてるの?」という時代だったのだ。
“脱ヴィジュ”と“ソフビ”「まだ化粧してるの?」
私がヴィジュアル系への違和感のようなものを感じたのは、LUNA SEAのミュージックステーション初登場時(1994年)である。それまでロックに興味を持っていなかった女の子たちが次の日から「LUNA SEAのヴォーカル、カッコいい」と言い出したことをよく覚えている。ただ、自分が覚えた違和感は、そうした世間の反応ではなく、“髪を切ったRYUICHIの姿”だった。このシーンのバンドマンといえば、浮世離れした派手な長髪がシンボルだったし、ミステリアスな雰囲気を醸し出す大きな役割だった。しかし、この時期、RYUICHIを筆頭に、櫻井敦司(BUCK-TICK)、YOSHIKI(X JAPAN)、hyde(L’Arc〜en〜Ciel)といった面々が次々と自慢の長髪をバッサリと切ってしまった。TUSK(Zi:KILL)は化粧も落とした。それは当人たちにとって、もう外見の奇抜さは必要ないという訣別の自念があったようにも思うが、シーンで見れば、ひとつの様式美の終わりのようであり、ヴィジュアル系黎明期、黒服系の終焉だったと思っている。
しかし、時はまだヴィジュアル系ブーム前夜である。すでに先人たちは「まだ化粧してるの?」といった“脱ヴィジュ(脱・ヴィジュアル系)”モードになっている最中に出てきたのが、SIAM SHADEだった。インディーズの頃はバッチリ粧し込んだ黒服バンドであったが、方向性の転換によりメイクをやめて、みんなで海水浴に行き、おもいっきり日焼けしたというのはファンの間で語り継がれる微笑ましいエピソードのひとつ。1995年のデビュー時は硬派なハードロックテイストのバンドといった印象だったが、いつのまにかヴィジュアル系の括りに入れられていた。SOPHIA(1995年デビュー) しかり、その畑とは無縁の音楽テレビ番組『えびす温泉』から出てきたCASCADE (1995年デビュー)までもヴィジュアル系の括りになっていたのは、テレビ番組『Break Out』の功罪のような気がしてならない。うかうかしていると、筋肉少女帯やシャ乱Qすらもヴィジュアル系とされてしまう時代である。そんな中、「我々はヴィジュアル系ではない」としきりに言い張ってたTHE YELLOW MONKEYの吉井和哉と、「そういうので“括る”ことを仕事にしている人もいるわけだから」と達観の域に入っていたhideをよく思い出す。いわゆる短髪で耽美臭がしない爽やかなヴィジュアル系バンドを“ソフビ(ソフト・ヴィジュアル系)”と呼んでいたのだが、この呼称はあまり浸透していたなかったことを後年になって知った。BUCK-TICK『惡の華』やX『Jelousy』の退廃美溢れるジャケットアートワークこそが至高と思っていた世代にとっては、非常にモヤモヤとした時代であった。
そんなモヤモヤを一切断ち切ってくれたのは黒夢だった。古き良き退廃美を継承したバンドながらもメジャーデビュー以降のファッショナブル傾向。そして一気にパンキッシュ路線に突っ走った男気に魅せられたロックファンは数知れず。思えば黒服系〜ソフヴィ〜パンクという、移り変わりの激しい90年代のJ-ROCKシーンを象徴するような路線変更だった。
ヴィジュアル系からミクスチャーへ
先述の「黒服系総洋楽化」を象徴するような印象的な映像がある。Die In Cries『LAST LIVE 95.7.2』のラストだ。解散後はサイドプロジェクトではじめたBLOODY IMITATION SOCIETYを本格始動させることが明らかであった室姫深が、長年愛用してきた“♂♀”ギターを客席に放り投げてしまう。本人は「“室姫深”との訣別」の意を込めた行為であったことをのちのインタビューで語っているのだが(ギターは、手にしたファンから本人の元へ返されている)、いろいろな想いが駆け巡る感慨深いシーンだ。それはまさに耽美なヴィジュアル系からラウドなミクスチャーロックへ移り変わっていく音楽シーンを象徴する場面だと思えてならない。ミクスチャーロックも和製英語であり、ある意味日本独自に発展したロックでもあるだろう。そこから今日に至る“ヴィジュアル系ラウドロック”へと繋がっていくのだ。
90年代末になると、いつのまにか『Break Out』がメロコアバンドの番組になっていた。一世風靡したヴィジュアル系ブームは終わったのだ。
「ヴィジュアル系ではない」と言い切ったL’Arc〜en〜Cielは一抜け、X JAPAN、LUNA SEAはブームに幕を引くかのようにシーンから去っていった。唯一残ったバンドについて、「BUCK-TICKはヴィジュアル系なのか?」という論争が2000年代中期まで続くのだ。
<中編へつづく>