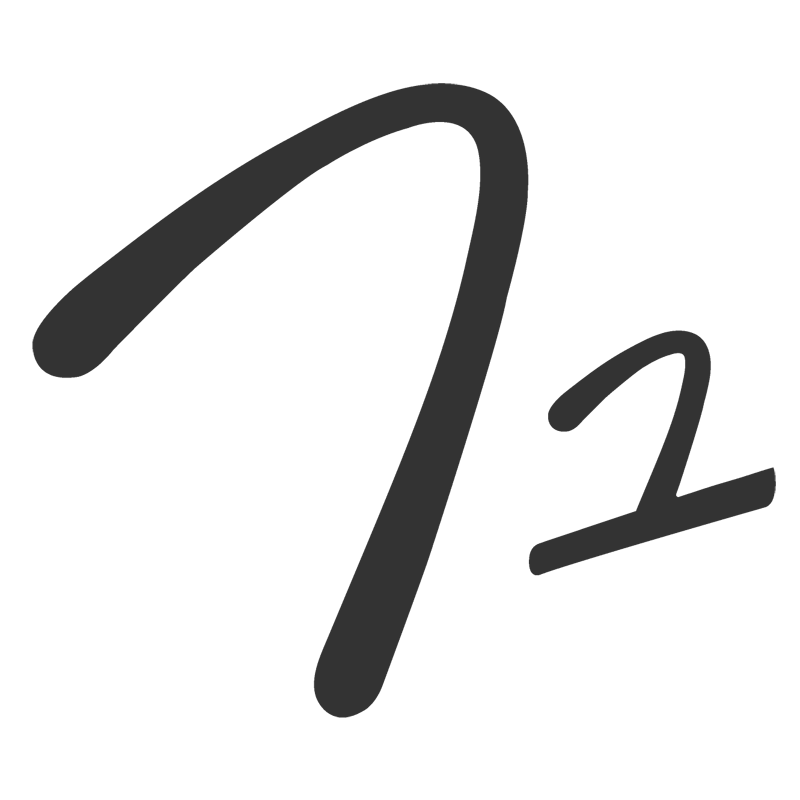昨夜、Twitterで流れてきた情報に目を疑った。
なんというか、思うことは多々あれど、ここ数年の行動・言動を振り返ってみればとも。現段階で色々言うのもどうかと思うのでしまっておく。
ただ、丁度その情報が流れてきたあと、テレビ番組に長渕剛が出た。自らの音楽と共に歩んだその生き様をターニングポイントを軸に語っていた。
剛はその尋常ではない肉体改造で、歌とともにそこから発するパワーは年々増してる。ああ見えて子供の頃はぜんそく持ちだった。折れてしまいそうな細い脚だった30歳くらいのときに「あと10年」という言葉をよく使っていた。表面上では解っていても、その言葉の裏にある真意を本当に理解できたのは、ずっとあと、自分が歳を重ねてからだ。
なんとなく、長渕剛というアーティストの将来に不安を覚えた時期がある。丁度アルバム『Captain Of The Ship』の頃、1993年あたり。“インドかぶれ”ともいうべき時期だ。継ぎ接ぎのだらけの民族衣装にバンダナ、極度に声もしゃがれていた声で生と死について生々しく歌う。このままガンジス川にのまれて、おかしくなるんじゃないか、ヨボヨボに衰弱していくじいさんのようになっていくのではないのか。シワシワに年老いてしまった長渕剛なんて見たくなかったんだ。だからそれを考えれば、方向は斜めに行ったけど、現在の姿はアリなんじゃないかと思っている。
「作品よ、残れ。作品だけは残れ。」
番組最後のこの言葉が突き刺さる。
私が音楽にどっぷりとハマっていったきっかけ、音楽・歌に目覚めたのが、長渕剛で、ロックに目覚めたのがヒムロックだった。
音楽趣味の嗜好が変わって行く中でもこの二人は別のところに居た。都合の良い言い方をするのなら、“神様”だとか“殿堂入り”なんて言葉を用いるのだろうが、何かが違う。全てを受け入れる、肯定するわけでもなく、正直「ふざけんな!」と思うことだってある。
言わば、そこを踏まえた安心感とでも言うか。実家みたいなものだ。
この二人はいつだって変わらない歌と音楽をやっていた。もちろん、時代の流れとともにサウンドの変化やアレンジの幅を拡げることはある。ただ、ロックバンドがヘヴィロック化していったり、ノイズや前衛的な音楽をやるようなことはない。いつの時代だって同じだ。
あの頃のように四六時中聴いてるわけではない。雑誌等のインタビュー記事をくまなくチェックするわけでもない。シングルは買わなくなった。リリースされるアルバムを予約をせずに思いだしたように購入し、ツアーがあれば、最低1回は行く。その程度だ。熱心とは言い難いが、そういった数年に一回あるかないかの行為が自分自身を見つめなす大事なこと。そんな大切な存在である。
洋楽を聴くようになり、アメリカ、ブリティッシュロックやオルタナ・グランジ、モダンヘヴィネス、ヒットチャートや商業音楽を否定したときだってある。ノイズだってインダストリアルだって、そんなマニアックな音楽にのめり込んだのも、帰ってくる場所があったからなのかもしれない。
ヒムロックと長渕、やってる音楽も表現も方法論も全く違う。共通項があるとするのら、己にストイックな完璧主義者だということか。
私が二人にのめり込み始めた当時の80年代は同じレコード会社・東芝EMI、同じ事務所・ユイ音楽工房だったことに、なんとなく共通するものを感じていた。それは形式上だけではなく、子供心に感じてた嗅覚のようなもの。長渕がデビュー当時、ギター1本で全国を駆け回って居た頃の初代マネージャー・糟谷銑司氏はのちにBOØWYを担当し、解散後は布袋寅泰のプライベートオフィスの社長になった。子供ながらも感じてたあの“におい”は間違っていなかったと一人、ほくそ笑んだものだ。
2004年8月21日「長渕 剛 ALL NIGHT LIVE IN 桜島」、2004年8月22日「KYOSUKE HIMURO “21st Century Boowys VS HIMURO”」これは運命なのか、くしくもお互いのターニングポイントになるであろう、伝説のライブ日程が重なった。とてもじゃないけど、ハシゴできるとは思えないスケジュール。私が散々悩んだことは言うまでもないだろう。結果、自分のスケジュール諸々加味して氷室のほうを選んだ。
うん、何言ってるんだって話。昨日ヒムロックの思わぬ発表があった直後に剛が音楽人生を赤裸々に語ってるというのが。
「作品よ、残れ。作品だけは残れ。」
番組最後のこの言葉が突き刺さる。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00DG0IXR8/6haratandaimi-22/ref=nosim/” name=”amazletlink” target=”_blank” id=”btn2″>Amazon