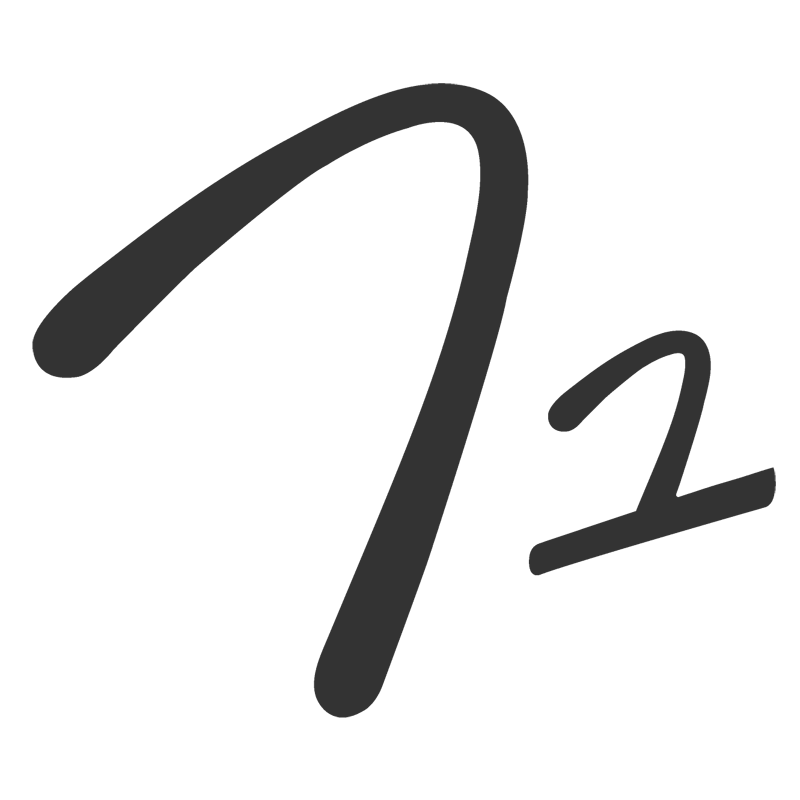中編からのつづき
90年代のBUCK-TICKやhideといったヴィジュアル系先駆者たちのオルタナティヴロックへの傾向は、“ミクスチャーロック”という日本独自のムーヴメントを起こした。ヘヴィロック、モダンヘヴィネス……、などとも呼ばれ、“ラウドロック”と呼ばれている現在のシーンに通ずるが、ここに挙げた音楽ジャンルのような言葉たちはすべて和製英語であり、日本だけの特異なシーンでもある。
80年代からのパンクやハードコアとジャパメタ、90年代の海外オルタナティヴロックが、ヴィジュアル系のカリスマたちによって融合され昇華された。しかしながら、一気に弾けてしまった。客がステージに向かってツバを吐きながら「かかってこいやー!」と殺気立っていたTHE MAD CAPSULE MARKET’Sのライブが、サークルやモッシュで両手を挙げて「オイ!オイ!オイ!」というピースフルなノリに変わっていったように。2000年頃、ちょうどHi-STANDARDが<AIR JAM>で絶頂を見せていた頃からその潮目は変わっていったように思う。
7弦ギターとダウンチューニング
ミクスチャーロックといえば、ラップヴォーカルにヘヴィサウンドという、Rage Against The MachineやLimp Bizkitに見られるスタイルが主流であったし、Linkin Park『Hybrid Theory』(2000年)の重厚なサウンドは、多くのバンドが目指すところだった。
KORNが使用して一躍広まった7弦ギターは、ダウンチューニング、ローチューニングに革命を起こした。7弦ギターはリュートとの非常に複雑な歴史があるのだが、それはまた別の話。当時、エレクトリック7弦ギターの設計とパーツ類のパテントはスティーヴ・ヴァイとアイバニーズが持っており、7弦ギターを使いたければアイバニーズのヴァイモデルを使用するしかなかった。しかし、ヴァイとアイバニーズが権利を解放したことにより、90年代末からさまざまなメーカーが7弦ギターの開発に着手。多くのギタリストたちがこの未知なる楽器を手にし、可能性を探り始めた。
ギター器材関係に明るくない人のために説明すると、ギターの一般的なチューニングにおけるの最低音は6弦解放のE(ミ)だ。ハードロックでは半音下げチューニングが用いられることが多く、Xなども6弦解放をD♯(レ♯)にしている。hideは6弦のみを1音下げるドロップDチューニングを好んでいた。「ROCKET DIVE」や「DOUBT」はD(レ)、「POSE」はさらに半音下げたC♯(ド♯)だ。これは当時のヘヴィネス急先鋒であったPanteraと同じチューニングだ。(厳密にいうと彼らはC♯より数セント分高い)
7弦ギターのチューニング最低音はさらに低いB(シ)であるが、本来の目的は低い音を出すためではなく、超絶技巧を得意とするスティーヴ・ヴァイが運指の可能性を広げるために開発されたものだった。しかし、KORNはそこを逆手に取り、さらに1音下げたA(ラ)を主とするサウンドを轟かせた。さすがにここまで低くなると、従来のギターアンプではその低音を再現することができず、アンプメーカーはより低音が出てよく歪むアンプを開発するようになる。「High Gain=ハイゲイン」時代の到来だ。
多くのギタリストやバンドは7弦ギターとローチューニングの可能性を模索したわけだが、結果的にはすぐに廃れてしまった。ミクスチャーロックのバンドは00年代初頭には激減。理由は多々あれど、“青春パンク”と呼ばれたメロコア勢に押されてしまった感もあったし、ライブハウスシーンは“下北系”の、UKロックやUSオルタナ勢のバンドが席巻していた。
ヘヴィサウンドとヴィジュアル系
当時の私は音楽専門学校で新人開発の仕事に従事しており、多くの学生たちの音楽活動とプレイヤーの資質を把握していた。メインストリームでは宇多田ヒカルと平井堅が流行っていて、シンガーを目指す者の多くはR&Bを歌い、アーティスト志向の強い女の子はみんな椎名林檎になりたがっていた。バンドマンたちは、第二のCoccoやYUKIを探している。ギターキッズが憧れるのは黒光りしたアーティストモデルでも、オーセンティックなフェンダーやギブソンでもない、ナビゲーターのレスポールモデルだった。そんな時代であったから、ヴィジュアル系を好む学生は少なく、彼らは肩身の狭い思いをしていた。
ちょうどその頃、ディスクユニオンの店頭でDir en greyのCDを見かけたのことが衝撃だった。当時のディスクユニオンといえば、今よりもっとマニア向けの店であり、中古買取にヴィジュアル系のCDを持って行こうものなら「これ、ウチでは値段付きません」なんて嫌味たっぷりに突き返されたものだった。自分の中でDir en greyといえば、YOSHIKIプロデュースでデビューし、クレームが殺到したミュージックステーション出演が印象に残っているコテコテのヴィジュアル系バンドだった。そんなバンドがなぜディスクユニオンにあったのか。
かつて多くのミクスチャーバンドを手掛けていた知り合いのレコーディングエンジニアによれば、ヘヴィサウンドの主流は今、ヴィジュアル系バンドに来ているのだと言う。Dir en greyを筆頭に、D’espairsRay、RENTRER EN SOI……、ああ、確かに90年代に聴きなれたダウンチューニングのヘヴィサウンドがそこにあった。そうしたサウンドがインターネットを通じ、海外のメタルファンにウケているという。なんでも、SlipknotとStatic XのメンバーによるMurderdollsのフロントマン、WEDNESDAY 13はDir en greyの大ファンらしい。そうした話題性から、ディスクユニオンはDir en greyを新しいタイプのメタルのバンドとして紹介していたのだ。
外資CDショップにヴィジュアル系のCDが売っていない時代
前回、「ヴィジュアル系は夏フェスに出られない」という話をしたが、「外資レコードショップはヴィジュアル系のCDを扱わない」時代があった。今となっては信じられない話かもしれないが、BUCK-TICKやXなどのドメジャーバンドは別として、タワーレコードやHMVにはインディーズなどのヴィジュアル系バンドのCDは置いていなかったのだ。ライカエジソンなどの専門店か、新星堂に行くしかなかった。
新宿にタワーレコードが出来たのは1998年。「INDIES(インディーズ)」と「J-POP/ROCK(メジャー)」という売場分けをした画期的な店だった。これもミクスチャーロックブームによるところが大きい。タワーレコード渋谷店や、HMV横浜店といった超大型店舗はいち早く「J-PUNK/HARD CORE」といった売場を設けていた。
そうした外資レコードショップにヴィジュアル系コーナーが出来たのは遅く、00年代中盤くらいから徐々に扱いが増えはじめたものの、とくにタワー渋谷店に本格的なヴィジュアル系コーナーが出来たのは界隈で最も遅かった。<V-ROCK FESTIVAL>(2009年)の開催が発表された頃であったと記憶している。
私が音楽プロダクションでレーベルのA&Rを勤めていた頃、脱ヴィジュアル系を目指すバンドを担当していたことがあった。関西を拠点としていた彼らは大阪/江坂/京都MUSEでのワンマンをソールドさせるヴィジュアル系バンドだったが、レーベル移籍とともに上京、そしてメイクをやめた。脱ヴィジュアル系の第一歩がアルバムをタワーレコードで扱ってもらうことだった。そのためにさまざまな施策を取った。ジャケットにアー写を載せない、黒や紫といった色をアートワークに用いない、などなど。「ヴィジュアル系とヤクザは本人が足を洗ったつもりでも、周りはそう見てくれない」とはよくいったもので、化粧を落としたところで雰囲気でバレてしまう。そこそこ人気のあったバンドであればなおさらだ。アートワークの色使いに関しては説明するまでもないだろう。赤や黄色といった奇抜な色を用いた。それが功を奏したのか、一部の店舗ではなかったが置いてもらうことができた。もっとも、潤沢な販促宣伝費があればこうした苦労も必要ないわけだが、インディーズの新人バンドなのだから仕方がない。2006年の話だ。
“ヴィジュアル系”ならぬ、“SHOCK ROCK”
ちょうどこの頃、2005年から3年計画で<independence-D>というイベントが音楽制作者連盟によって毎年開催された。電機メーカーのレコード会社や日本レコード協会といった、日本ならではのメジャーとインディーズという枠組みでなく、海外スタイルにならってレーベルが主体となり、日本と海外入り混じったインディペンデントのコンベンション型のフェスである。<HIP HOP/R&B>枠からは餓鬼レンジャー、ラッパ我リヤ、<PUNK/HARD CORE>枠からはFACT、マキシマム ザ ホルモン、9mm Parabellum Bullet、<METAL/SHOCK ROCK>枠からBALZAC、COCOBATといったバンドが新木場STUDIO COASTに集った。注目すべきは<METAL/SHOCK ROCK>枠にムック、メリー、蜉蝣、といったヴィジュアル系バンドが出演していたことだ。
このイベントには「日本から世界へ」という主旨もあった。協賛はMyspaceとディスクユニオン。先述の通りディスクユニオンがDir en greyに注目した要因に海外評価があり、海外の音楽ファンはMyspaceを通じて日本のバンドを知った。海外のオルタナティヴロックが日本で独自の進化を遂げ、ミクスチャーロックとなり、ヴィジュアル系バンドへと引き継がれていった。ヘヴィサウンドと奇抜なルックス、そんな日本のヴィジュアル系バンドを海外では“SHOCK ROCK”と呼んだ。
Dir en greyはDIR EN GREYへ。大文字表記となり、「英語で歌わないと世界では通用しない」と言われていた中で、日本語のまま本格的な海外進出を果たす。そして、KORN主宰<THE FAMILY VALUES TOUR 2006>に参加。名実ともに世界最高峰のヘヴィバンドの仲間入りを果たした。それは、どこか肩身の狭い思いをしていたヴィジュアル系バンドにとって、希望であったことはいうまでもないだろう。
<independence-D>で、もう一つ注目すべきは、「ヴィジュアル系」という言葉を一切用いなかったことだ。当時のヴィジュアル系シーンはキラキラ煌めいたバンドと、ヘヴィでダークなバンド、という二極化が進んでいた。後者のバンドの多くは、かつて90年代の黒服バンドがそうであったように、洋楽へと傾向し、脱ヴィジュアル系の兆しを見せていた。現にDIR EN GREYはノーメイクで活動していたし、ムックはメイクする場をわきまえるようになり、Guns ’N Rosesのオープニングアクトなどの際は、ノーメイクにTシャツといった出で立ちでライブを行なっていた。そんな彼らにとって、何かと誤解と偏見を産む“ヴィジュアル系”よりも、“SHOCK ROCK”という言葉は都合の良いものだったのかもしれない。
しかし、2007年5月にアメリカ・ロサンゼルスにて行われた<J-Rock Revolution Festival>によって、「ヴィジュアル系=Visual-kei」という言葉が一気に広まった。国内においても、ヴィジュアル系の語源がXの「PSYCHEDELIC VIOLENCE CRIME OF VISUAL SHOCK」だとしきりに言われるようになったのもこれがきっかけだった。欧州におけるVisual-keiブームを作ったドイツのレーベル<岩神 Gan-Shin Records>は、ヴィジュアル系をはじめとした日本のバンドの音源を数多く欧州諸国に流通していたが、中には「日本のバンドはすべて“Visual-kei”」という誤解も生まれ、「THE BACK HORNはヴィジュアル系なのか?」という海外での論争を見たことがある。もっとも、いわゆる“ロキノン系バンド”も、アニメのタイアップなどにより海外を視野に入れ、どこかヴィジュアル系を意識しているような展開をしていたのこともあったのだが。
ヴィジュアル系がカッコ悪いものではなくなった時代へ
そうやって、海外のVisual-kei人気がこれまであったヴィジュアル系の閉塞感を打破しつつあったわけだが、国内においてヴィジュアル系の名誉回復に大きな影響を及ぼしたのは、2007年、LUNA SEAの復活だった。X JAPANはHIDEの不在やTOSHIの問題を抱えたままの復活であったため、賛否両論があった。
この一報に多くのバンドマンたちが昔、LUNA SEAが好きだったことをカミングアウトしだす。00年代中期、ヴィジュアル系氷河期とも言われた時代に活躍していたヴィジュアル系以外の20代バンドマンたちはみんなLUNA SEA世代だった。彼らが10代だった90年代後半、世界でもっとも売れたギターはESPのINORANモデル、世界でいちばん売れたベースはESPのJモデル(ともに廉価ブランド含む)と言われるほどの影響力を誇っていた。みんなLUNA SEAでロックをはじめたのだ。しかし、いつのまにか「LUNA SEAが好きだった」ことを口にしなくなった。「“実は”昔、LUNA SEA好きだったんですよ」「“ここだけの話”、はじめて買ったギターはINORANモデルなんです」という“楽屋話”を何人何十人のバンドマンの口から聞いたことか。それだけ“過去のバンド”になっていた。それが復活によって、有名バンドマンたちの口からカミングアウトが発せられると、厳戒令が解かれたように次々と皆LUNA SEAが好きだったことを公の場で口にするようになった。それは同時に昔のヴィジュアル系話にも花を咲かせることにも繋がった。思い返せば、あれがヴィジュアル系が過去の遺物でもカッコ悪いものでもなくなった瞬間だったのかもしれない。
<おしまい>