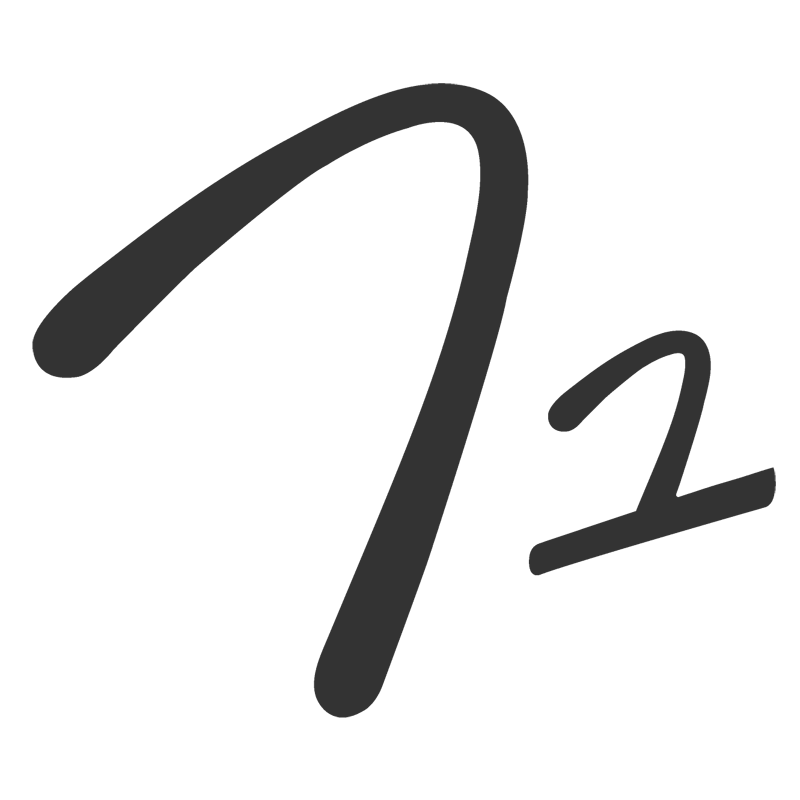クラシック音楽には「現代音楽」と呼ばれるものがある。ドイツ語では“Neue Musik”、英語では“20th century classical music”などと呼ばれるように、「20世紀以降の〜」といった趣であり、その定義は曖昧であるものの、無調、不協和音や変拍子といった、従来の音楽様式にとらわれない先鋭的な音楽を指すことが多い。
そんな中、ここ10年くらいで急激に広まったのが「ポストクラシカル」と呼ばれる音楽だ。当初は「ネオクラシカル」をはじめ、いくつかの呼称が存在したが、ここ数年で「ポストクラシカル」が定着した。わかりやすくざっくり言うと「クラシック+エレクトロニカ」である。クラシックのおおらかさとエレクトロニカの革新性を併せ持つ新時代の音楽。とはいえ、クラシック音楽よりも、アンビエントなどのニューエイジ音楽に近い部分もあったりと、その線引きはかなり難しいところもある。
北欧のアーティストたちを中心としたインストゥルメンタルのポストロックバンドやエレクトロニカ&フォークトロニカの人気もあり、クラシック音楽を普段聴かないようなロック&ポップミュージックファンからも支持されやすい。古典的なクラシック音楽は高貴な雰囲気から敷居が高く、現代音楽はマニア向けでありスノビズムである。そんな中で、メランコリックでノスタルジック、どこか抒情的であり親しみやすさのあるポストクラシカルはまさに日常と芸術の間に横たわる音楽なのかもしれない。
Jóhann Jóhannsson
映画『メッセージ』。予告で観て直感的に観なくてはならない映画だと感じたし、実際観た衝撃は大きかった。初回と2回目以降で印象が異なる映画であることはすぐにわかったし、“殻”もヘプタポッドの文字も映像も何もかも美しくて。そして、見終わった後のなんとも言えない感覚が忘れられなくて何度も劇場に足を運んだ。映画を観てから原作を読んだのだが、こんなにも哲学的で禅問答を思わせる原作からあのような映画に仕上がったのかと、その凄さを改めて感じた。「エイリアンがやってくる映画」と聞いて肩透かしを喰らったSF映画ファンもいたようだが、ウロボロスな物語であり、いろんな意味を持たせながら考えさせられる内容は個人的に思いっきりハマってしまった。おかげで未だに、静かな朝に小鳥のさえずりが聞こえると、ヘプタポッドが降りてくるような気がしてならない病気にかかっている。
そして、映像の美しさをさらに引き立て、神秘性がありながらも不穏な雰囲気漂う作品の世界に深く引きずり込んだのはヨハン・ヨハンソン(Jóhann Jóhannsson)の音楽だ。ミニマルながらも壮大で、前衛的ながらどこか懐かしい。不安を掻き立てられながらも、なぜか安らぎをも感じられる音楽。
ヨハン・ヨハンソンは1969年生まれ、アイスランドの作曲家。パンクロック、エレクトロニカなどのバンドを経て、2002年にUKのTouchからソロデビュー作『Englabörn』をリリース。弦楽オーケストラ、金管アンサンブル、電子ドローン、パーカッションなど、ミニマル+エレクロニカの融合……。本作と2004年の『Virðulegu Forsetar』を以って、ポストクラシカルの第一人者とされる。4ADやFat Cat、Typeなど世界の著名なレーベルから作品をリリース。
Max Richter
映画『メッセージ』において、神秘性とフィルターの掛かったような映像美をより一層際立たせていたのがヨハン・ヨハンソンであるなら、作品全体の物悲しさを決定づけていたのが、マックス・リヒター(Max Richter)の「On the Nature of Daylight」だ。弦楽五重奏とミニムーグのみで奏でられるミニマルミュージック的なものであるが、その旋律は情緒にあふれ感情的であり、心の隙間にスッと入ってきて思いっきり揺さぶられてしまう。
マックス・リヒターは66年生まれ、ドイツ生まれイギリス育ちの作曲家。エジンバラ大学、英国王立音楽院でピアノを作曲を学び、イタリアのルチアーノ・ベリオに師事。スティーヴ・ライヒの“6台のピアノ”等を再現したPiano Circusの創設メンバーのひとりでもある。
8時間に及ぶ眠りのためのBGM『SLEEP』など、その奇才っぷりを発揮しているが、なんといっても、誰もが知るクラシック音楽の名曲、ヴィヴァルディの『四季』を再構築した『RECOMPOSED BY MAX RICHTER VIVALDI – THE FOUR SEASONS』である。
編曲でなく、“再構築”であるのが注目すべきところ。ポピュラー音楽でいうリミックスに近い作業であるが、原曲の3/4の音符を排除しながらも原曲のイメージを損なうことなく組み立て直すという、まさに快楽主義的確信犯ともいうべき、奇才・鬼才アーティストである。
Ólafur Arnalds
オーラヴル・アルナルズ(Ólafur Arnalds)は、1987年アイスランド生まれの作曲家。映画音楽やクラシックのオーケストラの委嘱作品などを手がける一方で、シガーロスや坂本龍一などとの共演など、ポップフィールドでの知名度も高い。
ハードコアバンド、メタルバンドのドラマーという出自を持つ。元々、ロックと同等にクラシックが好きだったという彼は、バンド活動を並行して作曲活動を行っていくうちに、次第にバンド活動をやらなくなっていったという。
Joep Beving
自主制作アルバムのストリーミング再生回数が8,100万回を記録し、今年4月にドイツ・グラモフォンからリリースしたメジャー・デビュー作『プリヘンション(Prehension)』が本国オランダのApple Musicクラシック・ソング・チャートの1位から15位までを独占。今まさに世界が注目しているのが、オランダ出身のピアニスト、ユップ・ベヴィン(Joep Beving)だ。
立派に蓄えた髭に身長207cmと、そのワイルドな容姿とは裏腹に“不思議なセピア色を帯びている”と評されるそのピアノの音色は、これまで聴いたことのないような優しさを持った揺らぎである。
Akira Kosemura
小瀬村晶は1985年生まれ、2007年にオーストラリアの音楽レーベルからアルバム「It’s On Everything」を発表しデビュー。国内では、「三太郎」でおなじみのau KDDIのTVCMや、「ファイナルファンタジー」の楽曲制作、女性シンガーソングライターやなぎなぎへの楽曲提供など、映画音楽、舞台音楽、広告音楽を幅広く手掛ける。
“日常に捧げる新しい音楽の形”を提唱するその音楽は、親しみやすく、歌がないのにどこか唱歌的で煌めいていて。

Penguin Café
ブライアン・イーノの主催するオブスキュア・レーベルから1976年にアルバム「Music From The Penguin Cafe」でデビューしたのが、イギリスの作曲家、ギタリストのサイモン・ジェフスを中心とした楽団 ペンギン・カフェ・オーケストラ(Penguin Cafe Orchestra)である。
1997年にサイモン・ジェフスが他界してから実質的な活動は中止されていたが、2007年にジェフス没後10周年コンサートが行われた。そして、サイモンの実子であるアーサー・ジェフスを中心に、2009年にメンバーも一新された、新生“ペンギン・カフェ”が活動開始。
クラシックで使われる「小品」という日本語訳が語感含めて好きだ。英語では“piece(s)”、ドイツ語では、“Charakterstück”という、10数分に及ぶソナタ(伊:sonata)に対して、5分程度の短めの作品を指す言葉だが、個人的には古典的な室内楽を土台としながらも民族音楽、現代音楽など様々な音楽を高い演奏力を以って奏でるペンギン・カフェの音楽が、ものすごく「小品」っぽくてたまらなく好きだ。