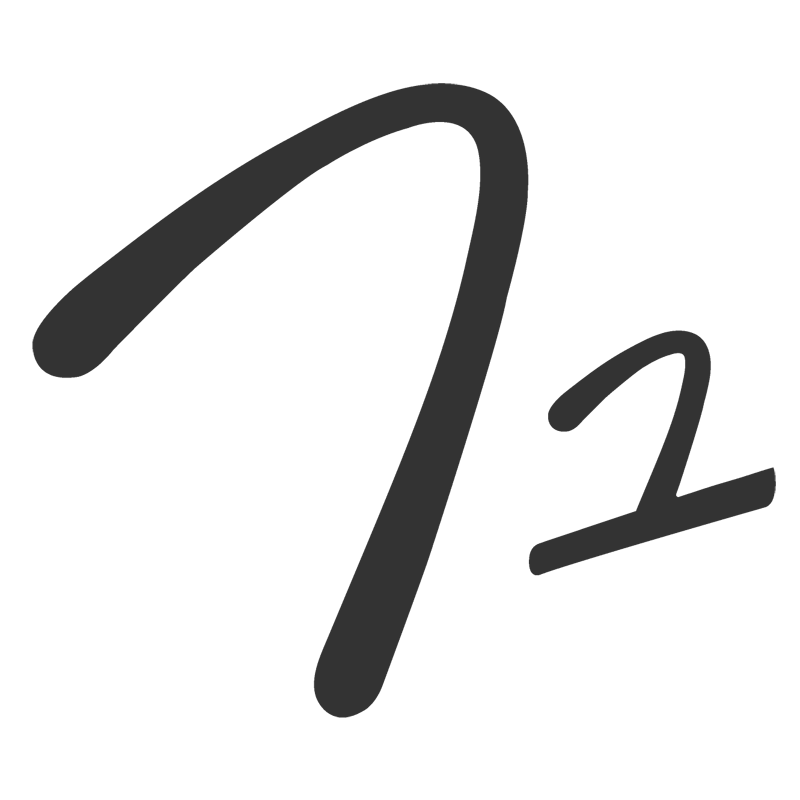前回からのつづき。
近年のラウドロックが解放的になったのは、ひとえに大規模な音楽フェスの影響が大きいとも思っている。俗に“フェス特化型”などともいわれる「ノリやすい、湧きやすい曲」が増えた。もっといえば、楽曲自体のBPM(テンポ)が上がったことは、ロックシーン全体に置いてよく指摘されることだが、ラウドロックにおいてはキャパシティの巨大化による楽曲の持つスケール感の増大を求められていったようにも思える。もちろん、映画『ボヘミアン・ラプソディー』にも登場する<LIVE AID>のようなアリーナ規模のイベントは古くから開催されてきたわけだが。80年代はそれこそQueenに対するSex Pistolsといった、オールドウェーブに対するニューウェーヴの台頭が新しいムーブメントを起こしてきたわけで。90年代のラウドロックに至るオルタナティヴロックの勃興は、Nirvanaのカート・コバーンがロックスターになることを嫌ったように、商業音楽への反抗のみならず地位や名声を手に入れることが成功ではない、という風潮が大きかった。現に日本においては、バンドブームからタイアップ至上、CDバブルへと移り変わっていく中で、“売れる”ことに対する執着が薄れてきた部分もあった。「武道館でライブやりたいとは思わない」「売れたいとは思わない」……ビジネス主義に寄ることなく自己を貫くことを美学とするバンドが増えた。90年代のどこか内向的な音楽はそうした独特の閉塞感の中で生まれていった気がするし、であるからこそ音楽探求に没頭できた時代でもあったようにも思う。
そうした中での、1997年<FUJI ROCK FESTIVAL>の開催は大きな意味を成した。大規模なスケールもさることながら、海外アーティストと同列に並んだ日本人アーティストである。それまで海外アーティストは憧れの存在であり、共演することは“前座”であることがほとんどだったのだから。洋楽に追いつけ追い越せだった日本のロックシーンが、ようやく海外と足並みを揃えることができた、……と言い切ってしまうと語弊があるのかもしれないが、そんな“勘違い”は日本の音楽シーンを大きく発展させたように思う。
“スケール感”という意味では、前回取り上げたONE OK ROCK『Eye of the Storm』が見せたものはバンドの進化ともいえるし、さらなる高みを目指すため、とも捉えることができる。逆に悪い言い方をすれば、「大人しくなってしまった」なんて思うのかもしれない。しかし、こうした音楽変化は長いバンド歴で見ればよくある話であるし、後年になって分岐点などと言われるアルバムだったりする。バキバキの変態インダストリアルをキメ込んでいたIncubusが『Morning View』(2001年)で突如メロディアス路線にシフトしたことをふと思い出してみたり。Red Hot Chili Peppersの『Californication』(1999年)はこれまでの“おバカ”路線をやめ、今日に至るモンスターバンドとしてのポジションを確立たきっかけにもなったアルバムだ。ちなみにRHCPといえば、オルタナティヴロックの雄、Jane’s Addictionのギタリスト、デイヴ・ナヴァロを迎え、ファンクからロック色を強めた『One Hot Minute』(1995年)が、ミクスチャーラウドロックの金字塔というべき名盤であることを忘れてはならない。そして、<FUJI ROCK FESTIVAL ’97>のヘッドライナーは彼らだった。
ライブ会場のスタンディング化
<FUJI ROCK FESTIVAL ’97>には、日本の90年代オルタナティヴロックシーンを象徴するバンドが出演している。THE MAD CAPSULE MARKET’Sである。客からのツバの洗礼を受けていたパンクバンドがデジタルを取り入れながらワールドワイドにラウドロックへと昇華していく活動歴は日本のオルタナティヴロック史そのものだ。ラウドロックがメロコア勢力に押されていく中で、確固たる地位を確立した数少ないバンドである。メジャーデビュー以降、その人気とともに渋谷公会堂、日比谷野外音楽堂、とキャパを広げていったわけだが、反面で客席スタイルの会場に馴染まなかった部分があったことは否めない。そんな中での赤坂BLITZのオープン(1996年)は、MADの人気のみならずシーンの需要を象徴するようでもあり、さらなる活性化へと後押しするようにも思えた。
スタンディング形式の一般化は、赤坂BLITZのオープンを皮切りに、Zeppが札幌(1998年)からオープン、SHIBUYA-AXオープン(2000年)、CLUB CITTA’ 移転(2000年)、ON AIR EASTからO-EASTへの建て替え(2003年)、と、1500人〜2000人強規模のライブハウスがライブ会場のスタンダードになっていくわけだが、そこにとどまっていない。かつて千葉県浦安市にあった東京ベイNKホールは、舞浜という立地と、海外の宮殿を思わせる外観から高い敷居のイメージが強いホールであったが、KORNが初来日単独公演(1999年)にこの会場でスタンディング形式を用いたことで情勢は大きく変わった。6000人規模のスタンディング会場として使用されることが多くなったのだ。それまでは消防法的な問題もあったのだろう、これほどまでの規模の会場がスタンディグで使用されることはなかった。しかし、これを機に横浜アリーナ、そして日本でいちばん規制の厳しい会場と言われる、日本武道館までもスタンディング形式でのライブが開催されるようになった。
デジタルレコーディング
機材器材は90年代後半にかけて大き変わった。ギターアンプのハイゲイン化、サンプラーなどの登場、シーケンスの同期、そして何よりPro ToolsといったDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)に代表されるデジタルレコーディングは、従来の概念を覆すものとなった。
ラウドロック界のギターサウンドに革命を起こしたのが、Linkin Parkである。『Hybrid Theory』(2000年)で聴ける、これまでのヘヴィさや歪みという概念とは違う、聴覚上を音の壁で覆い尽くしたようなサウンドは、多くのバンドマンやレコーディングエンジニアを魅了した。かつて布袋寅泰が、無機質感を出すためにアンプを使用せずに『GUITARHYTHM』(1988年)を作った。BUCK-TICKの今井寿はギターらしからぬ音を求めてギターシンセを取り入れた。hideは重厚なサウンドを作るために、複数のギターを重ねて録音していく従来の手法ではなく、1本のギターを異なるメーカーの複数のアンプで鳴らす手法を取っていた。……そうした中、アンプシミュレーターにプラグイン、デジタル機材の発達によってサウンドの幅は一気に広がったのだ。HR/HMのメタリックなサウンドではなく、パンキッシュな荒々しさや粗暴的なサウンドでもない。音の解像度が高く密度の大きい分厚いサウンドが好まれるようになったのだ。低音域から高音域までダイナミックレンジの広いサウンドである。とくにギターはこれまでの以上の広い音域を補うようになった。
デジタルにおけるギターレコーディングで多く用いられる“リアンプ”という手法がある。簡単に説明すると、アンプを用いらないエレクトリックギターのクリーンな音をあらかじめデータ録音しておき、後からそのデータをアンプで鳴らしてレコーディングしていく作業だ。この手法を用いれば、音作りをしてプレイする、それをレコーディング、そして確認、という通常の作業を、“プレイ自体の録音”と“アンプから出る音を確認しながら録音”という2つの作業効率化できる。もっといえば、ギター自体はあらかじめ家で録っておけば、スタジオではアンプの音作りだけに集中できるというわけだ。実際のアンプで鳴らすため、シミュレーターの弱点である“デジタルっぽさ”がないことも利点である。
このリアンプという作業は、ギターサウンド自体が楽曲の色や音楽性を担うロックのジャンル、とくにディストーションギターで壁を作るようなラウドロックの世界では広く用いられている。ただ、デメリットもある。プレイの録音段階ではアンプを用いないために、ピッキングの強弱などの細かいニュアンスはなくなる、というか、つけられない。“エレキギターはギターとアンプがあってこその楽器”という根本を切り離してしまう手法だからだ。そのため、ブルースやジャズというような繊細さやフィーリングを大事にするようなギタリストには好まれない。
ベースという役割
ギターとベースが同じフレーズを弾く“ユニゾン”があるが、フレーズのならずサウンドまでもギターとベースが同化しているアルバムがある。THE MAD CAPSULE MARKETS『DIGIDOGHEADLOCK』(1997年)だ。元々、ギシギシに歪んだディストーションサウンドのベースを武器にしていたバンドだが、本作ではギターとベースの棲み分けがなく、フレーズとサウンドともに1つの楽器であるかのように一体化している。低音域をベース、中低音をギターという風に完全に一体化し、ひとつの弦楽器になっている聴感である。ギタリスト脱退に伴い、曲によってはTAKESHI “¥” UEDA(現・上田剛士 AA=)がギターもプレイしているため、タイム感までも完全にジャストになっているところも興味深い。
一般的にバンド全体のサウンドメイクとして、ベースとキック(バスドラム)、どちらを下(低音側)に置くか? という問題がある。一般的に「4つ打ち好きの日本人」と呼ばれるように、日本ではキックが下にいたり、アタックが強調されるほうが好まれるのだが、海外のロックにおいては古くからベースを下に置くことも多い。ラウドロックではKORNのフィールディーによるベースサウンドが革命を起こした。KORNの重さで大きな肝となっているのはギターでもキックでもなく、ベースにある。腹よりも胸にくる超重低音とスラップからはじき出される、耳を劈くアタック強めの高音が炸裂する“超ドンシャリサウンド”は、ラウドロックにおけるベースの象徴的なサウンドになった。マーカス・ミラーのアクティブ回路、そしてRHCP・フリーのMusicman Stingrayによるバチッとしたスラップのサウンドをさらに強力にさせたものだ。5弦ベースやダウンチューニングがピックアップされるKORNだが、低音だけではないのだ。高音を強調するため、ツイーター付きのベースアンプを流行らせた。低音を担うスピーカーがウーハーで、高音を担うのがツイーターである。つまり、ギターのみならずベースサウンドのレンジも圧倒的に広がったわけだ。
<つづく>