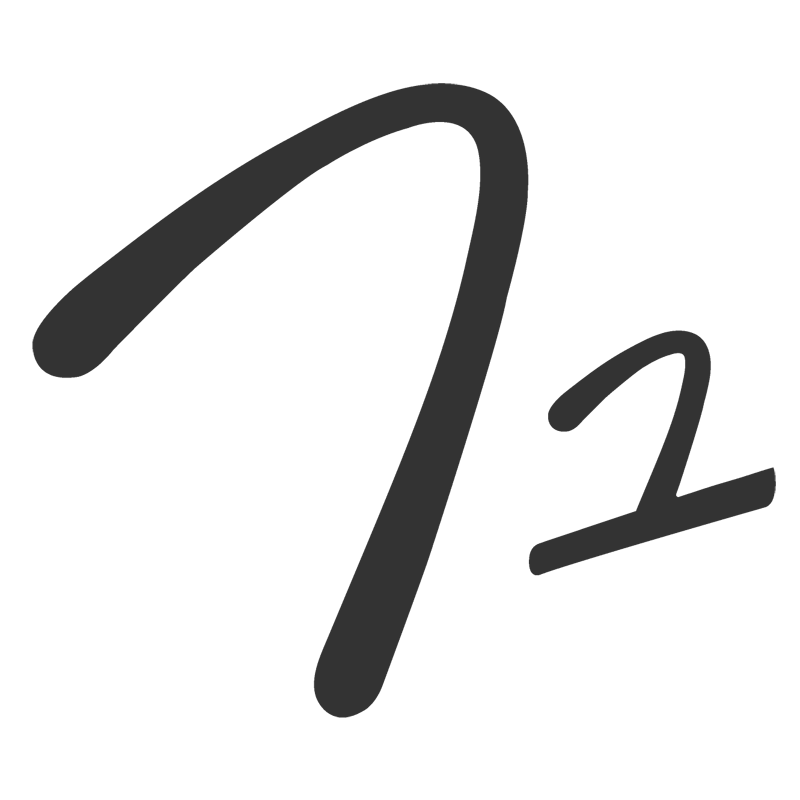ONE OK ROCKのニューアルバム『Eye of the Storm』が「洋楽っぽい」と評されていることについて。言わんとすることはすごくよくわかる。けれど、逆に「ワンオクっぽい洋楽バンドは?」と訊かれて思い当たるような海外のバンドはいないし、そもそも彼らの音楽は、ただ洋楽をなぞっているだけではたどり着けないものである。しかしながら、そう評されるのは「日本人が考えるステレオタイプの洋楽バンド」という虚像が、いまのラウドロックバンドに投影されているのだと思う。その代表格がONE OK ROCKというわけだ。昭和時代の若者が、THE STREET SLIDERSやRED WARRIORS、ZIGGYなど“バッドボーイズ”なバンドに、セックス&ドラッグ&ロックンロールなどこか“向こうの香り”を感じていたことに似ているのかもしれない。
先日、noteに書いたのだけれど、音楽性以前に「ONE OK ROCKは洋楽」という概念は今の10代にとって普通の感覚であったりもする。
最近のラウドロックバンドはヘヴィロックじゃないよね
そもそも、ラウドロックってなんだろう? 歪んだディストーションギターがガーッとしていて、ヴォーカルがエモくて……
「あれ? そんなにヘヴィじゃなくね?」
チューニングは低い、サウンドも分厚い。だけど、何かが違う。……ああ、ものすごく解放的なんだ。
全体的にサウンドが整理されていて、壮大さを感じさせる音像。ヴォーカルは美しいメロディであり、気持ちを高ぶらせながら、その叫びは外に向かっている。むかしのラウドロック、90年代はどこか内包的で、禍々しく不穏なイメージがあった。それに比べると今のラウドロックバンドは洗練されていて、ものすごくスマートな印象だ。
そもそも、“ラウドロック(Loud Rock)”とは和製英語であり、日本独自のものだ。“ヘヴィロック(Heavy Rock)”も“モダンヘヴィネス(Modern Heaviness)”も同じく和製英語であり、日本だけの中で発展してきた音楽なのである。
ラウドロックの勃興〜オルタナからミクスチャーロックへ
ドラマ主題歌やCMタイアップ、カラオケの市場も相まって、世はCDバブルへと向かっていく90年代初頭。BUCK-TICKやhideといった、ヴィジュアル系黎明期のアーティストたちが海外の最先端の音楽を咀嚼し始める。すでに“成功を収めた”アーティストたちが、メインストリームから距離を置いた音楽をやり始めたのだ。それは、Ministryなどのインダストリアルロックからの流れでもあり、Nirvanaに代表されるグランジを筆頭としたオルタナティヴロックの流れでもあり、“ブリティッシュインヴェイジョン”と呼ばれたニューウェーヴからの流れでもあった。そして、80年代からのパンクやハードコアのシーンも飲み込んで、いつしかミクスチャーロック(Mixture Rock)という日本独自のムーヴメントが出来上がっていった。
そうした海外意識の流れに乗れなかったバンドブーム期出身のバンドも多くいたわけだが、ジャンルとして淘汰されてしまったのがハードロック/ヘヴィメタルのバンドである。
HR/HMを古きものにしたモダンヘヴィネス
80年代にはジャパメタブームがあり、90年代初頭はMr.BigやBon Joviといった海外の“ギターヒーロー”的なバンドが日本でも大きく支持されていた。LAメタルも人気だった。しかし、ミクスチャーロックの勢力拡大とともに、「ギターソロはダサい」という風潮が蔓延していく。現にそう公言するギタリストも少なくはなかったし、メロディックスピードメタルのツインギターの代表格であった、X JAPANのhideは、ソロ活動を進めるにつれ、ギターソロの比重を大幅に減らしていった。
ギターソロの否定、いうなれば“テクニカル至上への反抗”という意味では、既に80年代のパンクロックの存在があったわけだが、ミクスチャーがそれと異なるのは、hideのようなHR/HM出身のアーティストが自ら音楽のベクトルを変えたところが大きい。
海外では、Metallicaがアルバム『Metallica』(1991年)で、これまでのスピード感のあるスラッシュメタルのアプローチからグランジ要素を取り入れたグルーヴ重視のどっしりとしたスタイルにシフトする。Pantera『俗悪』(1992年)、Helmet『Meantime』(1992年)ともに“Groove Metal”、日本では“モダンヘヴィネス”と呼ばれ、シーンに大きく影響を及ぼす。ジャパメタの重鎮、LOUDNESSもアルバム『LOUDNESS』(1992年)でモダンヘヴィ路線へとシフトした。ヘヴィメタルがヘヴィロック、ラウドロックになった瞬間だった。
その後、Rage Agaist The MachineやKORNの登場によって、テクニカルな技術面よりも獰猛なリフとヘヴィなグルーヴに重きをおくバンドは、国内でもどんどん増えていった。
DIE IN CIRESのギタリスト室姫深が、解散後に本格始動させたバンド、BLOODY IMITATION SOCIETYの『LOUDMAN』(1996年)というタイトルがこの時代を象徴していた。HR/HMとの差別化を図るため、“HEAVY”ではなく、“LOUD=騒々しい”という言葉を好むバンドが増えたのだ。ディスクユニオンとHMVが「LOUD/PUNK」というコーナーを設けたのもちょうどこの頃だ。
明確な括りというものはないが、オルタナティヴロックからのミクスチャーロック、従来のHR/HMから脱却したモダンヘヴィネス、パンク、ハードコア…… そうした音楽を総称して“ラウドロック”と呼ぶようになっていった。
ギターサウンドメイクのトレンド
そして、器材周りの発達は欠かせない。KORNが使用した7弦ギターはダウンチューニング、ローチューニングに革命を起こした。しかし、KORNが用いたLow-Aチューニングは、デビュー当時のアンプだとその重低音をきちんと再現出来ていないところも見受けられる。1stアルバム『KORN』(1994年)から、2nd『Life Is Peachy』(1996年)で劇的に向上したサウンドプロダクトは、器材・機材類の影響も大きいだろう。Mesa/Boogie DUAL RECTIFIER(1991年発表)を筆頭に、Hughes & Kettner TRIAMP(1995年発表)、Marshall JCM2000(1997年発表)など、パワーのあるギターアンプが次々と開発された。ハイゲインアンプ時代への突入である。
それによって、ギターサウンドのトレンドは大きく変化する。主流となったのは低音と高音を強調した“ドンシャリ”サウンドだ。HR/HMギターの醍醐味のひとつに、低音弦の高速キザミがあるが、そこを際立たせるためにハイ寄りのミッド(高音〜中音)を強調したサウンドメイクがある。そうすると、巻き弦にピックが擦れる音を含めて前に出てくるのだ。しかし、ミクスチャーバンドの多くはそうしたサウンドを「ミッドの濡れた音」として嫌い、その辺りの音域(800khz周辺)をバッサリとカットするのである。
わかりやすいところでいえば、Annihilator「Human Insecticide」(1989年)のジュグジュグしたメタル音と、「ミッドの濡れた音」が大っ嫌いだったISHIGAKIによるTHE MAD CAPSULE MARLE’S「パラサイト(寄生虫)」(1994年)で聴けるザクザクの超ドンシャリ音。奏法自体は同じなのに聴こえ方はまったく異なる。
こうして、「メタルは古い」「ギターソロはダサい」という風潮が蔓延していたわけだが、半面でメタルギターの“リフ”は重視され、Led ZeppelinやBlack Sabathといった、リフに重きを置いていたいにしえのHR/HMバンドは再評価された。中でも、テクニカル至上の火付け役となったVan Halenのエディ・ヴァン・ヘイレンは、真空管アンプのパワー管をギリギリまで追い込んだ“ブラウンサウンド”を武器に、その一斉を風靡したテクニカルなギターソロではなく、リフを含めた“バッキングの巧みさ”にあらためて注目が集まるようになった。
エディはプレイのみならず、器材方面での貢献度も大きい。シグネイチャーモデルのERNIE BALL MUSIC MAN EVH(ならびに、後継機種Axis)は、海外HR/HMギタリストのみならず、日本でもB’zの松本孝弘をはじめ、UNICORNの奥田民生やZi:KILLのKENといったジャンル問わず“音にうるさいギタリスト”が好んで使っていた。そして、エディとERNIE BALL MUSIC MANとのエンドース契約終了後、EVHに搭載されていたピックアップを市販用に改良したDiMarzio Tone Zoneは、Seymour Duncan JBと並んでヘヴィサウンドを好むギタリスト全員が使ったことがあるのではないかと思うくらい、みんな載せていたのだ。80年代のHR/HMブームにヒットした同社のSuper Distortionと比べると出力が低く、歪ませることよりも中低音の出方や太さに重きをおいていたモデルであり、この時代のギターサウンドを象徴していた。ハイゲインアンプの登場により、ギター側で“歪み”を稼ぐ必要性がなくなったわけだ。RATMしかり、KORNしかり、80年代のHR/HMや現在のラウドロックバンドよりも荒々しいサウンドであるが、歪み自体はそれほど多くはないのである。歪みより音色、音色よりもグルーヴで重さを出す。
器材機材周りの進化はさらに進み、アナログからデジタルのレコーディングへと変わっていく。そんな中、新たなギターサウンドを持ったバンドが注目を浴びる。Linkin Parkの登場である。
<中編へつづく>