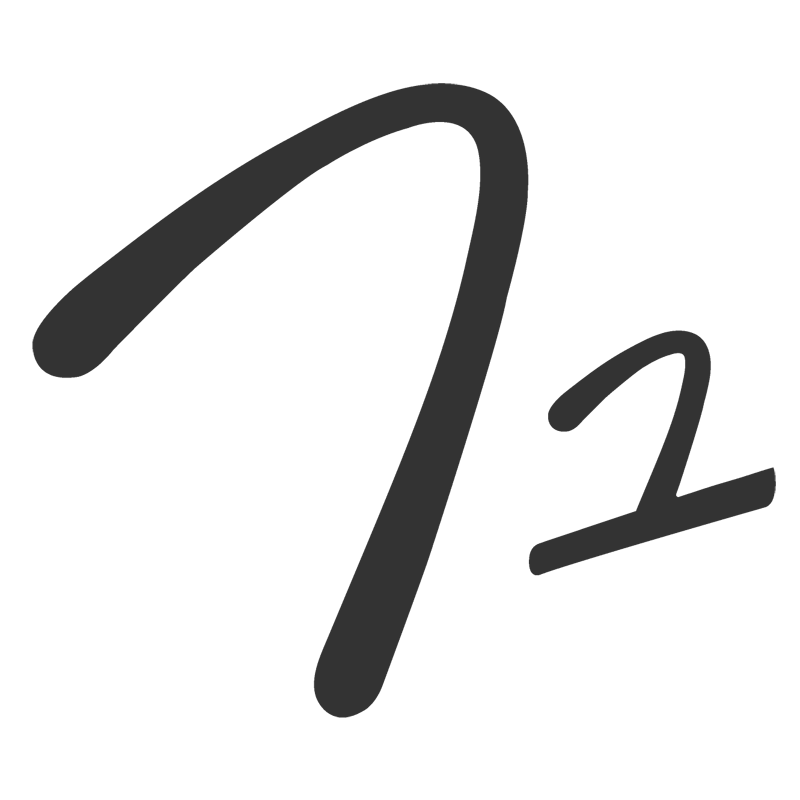少し前の話だが、LOUD PARKにthe GazettEが出演した。その発表があったとき、こんなことを書きました。
☞ ヴィジュアル系はいかにして海外で支持を集めたか? the GazettEらの活動に見る開拓精神 | リアルサウンド
the GazzetEのLOUD PARK出演から見る「ヴィジュアル系ロックバンドとしてのプライド」と、PIERROT、BUCK-TICK、DIR EN GREYなどの事例を基に、ヴィジュアル系の対外イベント・異ジャンルによる交わりという視点。
DIR EN GREYが本格的に海外進出を目指した2000年代中頃、いわゆる“脱・ヴィジュ=脱・ヴィジュアル系”をしようとしていた風潮がシーンにあった。結果としては海外でのヴィジュアル系評価があり、それはなくなったのだが。「ヴィジュアル系の偏見をなくそう」というムーブメント、そのサウンド面での象徴とも言えたのが、ラウドロックでありヘヴィサウンドであった。
なぜ、ラウドロックなのか。90年代中頃、KORNに代表されるような“モダンヘヴィネス”と呼ばれるバンドがアメリカから世界に台頭し、日本においても例外ではなく、その影響力は大きかった。日本独自の“ミクスチャーロック”はまさにその象徴ともいえるだろう。ただ、それはAIR JAMに代表されるメロコア・シーンに押されてしまい、2000年あたりをピークに徐々に衰退してしまった。ダウンチューニング、7弦ギターや5弦ベースなどを使用するミクスチャーバンドが減っていく中で、残ったのはヴィジュアル系譜のバンドたちだった。そこには、90年代初頭のインダストリアルミュージックの波及による、ヴィジュアル系黎明期アーティストたちによる洋楽化の影響が大きかったと思う。それをリアルに体感した、音楽に目覚めるきっかけとなった世代がシーンに頭角を現しはじめたのが、ちょうど2005〜2006年あたりであるように思う。
元来、ラウドロックはメインストリームを賑わすようなジャンルではない。ゴシックなどの耽美性から派生していった黒服系アーティストたちの、狂気や凶暴性、無機質感といった非現実的世界観を、見た目ではなくサウンドとして表現するに適していたともいえる。既に絶大な人気と影響力のあったhideなどが、いちはやくそれを取り入れたことにより、一躍脚光を浴びた節は大きい。90年代初頭〜中頃は時すでにバンドブームの陰りがあり、かつて絶大な人気を誇った多くのバンドが去って行った時代だった。そこで生き残ったのは、そういった先取りともいうべき音楽要素を取り入れ、独自の世界観を築いたアーティスト・バンドたちだった。この系譜は今でも当人たちの意識・無意識関係なく、ごく自然に一つのスタイルとして今でも確立されている。この当時の現象を私は勝手に「J-Rock総洋楽化」と呼んでおり、特に93年を一つの基準にしている。(☞ J-Rock総洋楽化「おれたちインダストリア充」の巻 - ジェイロック回顧主義 #3)
そんなラウドロック・スタイルの礎を築いたアーティストたちの中から、模範ともいうべき楽曲を紹介していきたい。あくまで主観である。
hide「DOUBT」(1993年)
https://www.youtube.com/watch?v=5yymjtHp4Mg
Nine Inch Nails、White Zombie、Jane’s Addiction… といった当時の最先端の洋楽を教えてくれたのは紛れもなくhideである。ダウンチューニングより繰り出されるヘヴィリフを主体としたインダストリアル・メタルを噛み砕いて解りやすく表現してくれた。このスタイルが言わずもがな、ヴィジュアル系はもちろん、日本におけるラウドロックの模範になったことはいうまでもないだろう。
攻撃的なリフにキャッチー感のあるメロディを落とし込む、hideのお家芸代表曲が「DOBUT」である。新バージョン「DOUBT ’97」のほうが知名度・人気はあるかとは思うが、シンプルながら攻撃性の高いリフの応酬と単調に繰り返すリズムだからこそ生み出される狂気。インダストリアルな醍醐味はオリジナルVer.が上。音楽業界を皮肉った意味を込められている歌だが、その怒りがゆえの破壊力。「DOUBT ’97」では歌詞の一節が省かれている。
MVのバックメンバーにはアメリカのオルタナティブ・ガールズバンド・L7が参加しており、国境を越えたhideの交友録を垣間見ることができる。のちの「BACTERIA」(1996年)MVではKilling Jokeのメンバーが登場しており、zilchへの結成に繋がっている。
BUCK-TICK「唄」(1995年)
hideと同様に洋楽サウンドを教えてくれたBUCK-TICKであるが、そのスタイルは非常に対照的。hideが洋楽要素を解りやすく提示していたのに対し、BUCK-TICKは実に難解だ。オマージュ元が全く見えないのである。あくまで推測であるが、hideは楽曲をひたすらコピーし、音楽構成要素を理解した上で自分のものにしていたと思われるが、BUCK-TICKは直感で得たものをセンスのみで表現しているだけのように感じる。コード進行などの音楽理論はおろか、ペンタトニック・スケールやブルーノートといったギタリストの教科書的な指クセすら存在しない今井寿の常識を覆す奇想天外なフレーズとメロディ。「唄」のイントロ「デコデコリーン、ばーん!ばーん!」の破壊力たるや。いい意味でギターをまともにやっていたら出てこないフレーズの応酬である。
Zi:Kill「Bad Man」(1993年)
ポジティヴ・パンクに代表されるイギリスのニュー・ウェイヴを色濃く出していたのがZI:KILLだった。どこか陰鬱で耽美な香りのあったバンドだが、アルバム『IN THE HOLE』(1992年)から劇的な音楽性の幅の広がり見せていく。斜に構えた感のあった黒服バンドの中では珍しい底抜けに明るい楽曲や、男臭さ漂うがさつな詞、アコースティックやホーンセクションなどの導入による、カラフルなサウンドはまさに唯一無二。ブリット・ポップに通ずる“ひねくれたポップ感”はシーンの中で頭一つどころか完全に抜きんでていた。とはいえ、ブリット・ポップブームの火付け役、Blur『Parklife』(1994年)の登場前でもあったことが興味深い。
そんなZI:KILLの完成形ともいうべきアルバムが『ROCKET』(1993年)であり、「Bad Man」である。人を喰ったようなようなTUSKの歌とコミカルさを感じさせながら次々と変わっていく楽曲展開が強烈なインパクトを与えるが、何よりバックのいかついサウンドである。長年イギリスの影響を受けてきたバンドの初のロンドン・レコーディングながら、このハードロックなオルタナティヴ感というのはイギリスよりもアメリカ寄りであり、2000年代のオルタナティヴ・ロック、Queen of Stone Edgeあたりを彷彿させるサウンドだ。
THE MAD CAPSULE MARKET’S「HI-SIDE」(1994年)
https://www.youtube.com/watch?v=ZCIAb1lJQdk
デジロックの代名詞とも云えるTHE MAD CAPSULE MARKETSだが、バンドの真髄はまだ“MARKET’S”カンマ入り時代の『PARK』(1994年)にあると思う。まだデジタルっぽさもヘヴィさも強調されておらず、パンク、ハードコア、ニュー・ウェイヴ、といったバランスが絶妙なのである。80年代のジャパニーズ・パンクを土台としながらも、前衛的なサウンドへの挑戦、それを堂々とメジャーでやっていたことは大きい。hideやBUCK-TICKなどの有名アーティストが絶賛していたことは、アングラなにおいを漂わせつつも斬新なことをやっていた新人バンドの、シーンにおいての位置付けを確固たるものとし、その影響力は計り知れない。のちのミクチャーシーンが形成されるきっかけとなったのは言うまでもあるまい。
「HI-SIDE」はラウドロックの常套句であるギター&ベースによるユニゾンではなく、それぞれが違うことをやって、グルーヴで重さを出していくというバンドマジックをこれ見よがしに見せつける曲。ギター・ISHIG∀KIの多彩なセンスによる味付けが肝だ。ベースが4弦開放からぬるぬると這いずるように上がって行くフレーズに対し、ギターは〈E→E♭〉というコードをひたすらスライドさせているだけである。アクセントとして、リズム隊そのままに、ギターだけ鋭いカッティングを交えながら〈D→E〉という音程とリズムの裏表がひっくりかえるフックを混ぜる。と思えば、一気に畳み掛けるような前ノリのユニゾンに変わっていく。テンポを速くする、音数を増やす、音色を変えるのではく、バンドのノリ、グルーヴだけで楽曲のメリハリをつけていくのである。レギュラーチューニングであり、ギターがそれほど歪んでいないことにお気付きだろうか。そして楽曲のキィはEだが、ギターは最低音である6弦開放のEを一度も鳴らしていないのである。この楽曲で聴ける一番低いギターの音は5弦開放のAだ。ヘヴィさは音色でもなければ、実際鳴らしている音の高低でもないということである。全体にみて、シンコペーション的に三拍目の“タメ”が命の楽曲である。このタメで、チューニングでは生まれない独特の重さを出す。ただフレーズをなぞるだけではこのヘヴィさは出ないだろう。「ヘヴィな楽曲はチューニングを下げて歪ませる」ことが当たり前だ思っている最近のバンドには是非見習ってもらいたいところだ。
そして、〈ヘヴィサウンド+ラップ調ヴォーカル〉という“ラップコア”スタイルを日本において確立させた楽曲であったことを付け加えておく。
SOFT BALLET「PILED HIGHER DEEPER」(1993年)
カルトな音楽ジャンルであったインダストリアルを大真面目にメジャーというフィールドで歌モノとしてやってのけたバンドだ。メンバーにギターが居ないことから他バンドに比べると、ラウドロックとしては馴染みの薄い感もあるが、デジロックが確立される前のエレクトロとロックの融合という意味で、アルバム『INCUBATE』(1993年)からの方向性は注目すべきだろう。無機質で反復される電子リズムに絡むギター/ベースというのはTHE MAD CAPSULE MARKET’Sも目指したところでもあり、「PILED HIGHER DEEPER」ではMADからCRA¥とISHIG∀KIが参加している。機械的なビートと無機質な弦楽器サウンドが独自の色を出すのに一役買っている。
Oblivion Dust「Trust」(1998年)
ギタリスト・KAZの〈hide with Spread Beaver〉への参加でその存在が広く知られるようになったOblivion Dustだが、「邦楽っぽくなさ」ではその前から群を抜いていた。「Trust」のイントロのコード感、歌始まりの展開から完全に日本人離れしていた感覚が解るはず。実際、ヴォーカルのKEN LOYEDがイギリス出身であったり、外国人メンバーが居たりと、納得する部分も多々あるのだが、なんといってもギターの太さである。バンドとしてはニュー・ウェーブの香りのする音楽性であるが、リフなどで露骨なヘヴィさを強調するわけでなく、ギターのサウンドメイクの分厚さでラウドロックっぽさを演出するという新らしいものだった。ジェミー・ロケッツというアメリカン・ハードロックバンド出身のKAZとKEN LOYEDのイギリスのアンニュイさ妙に溶け込んで独特の世界観を作っている。
Media Youth「キミの未来」(1998年)
そして、KIYOSHIもハードロックあがりのテクニカル系ギタリストであったが、スタイルを変え、あのストラップの長さだからこそ生まれたであろう、掻きむしる手首のピッキングとタイム感は絶妙である。「キミの未来」はヘヴィなサウンドとキャッチーなメロディー、スピード感、そしてメジャー感。どれをとってもJ-Rock/V-Rockの模範ともいうべき楽曲である。ここにあげてきた曲はどちらかと言えば、ヘヴィサウンドやリフとリズムが前提としてあり、それを軸にした楽曲構築が形成されていることに対し、同曲は歌を中心とした楽曲がまずあって、そこにヘヴィ要素を肉付けしていくアレンジという印象を受ける。
ヘヴィなリフのイントロ→不安定なAメロ→捲し立てるBメロ→一気に開放されるサビ、という起承転結ともいうべきメリハリを利かせながらスリリングに展開していく楽曲構成、全てにおいて一切の隙がない。今まであげた中では一番メジャー感があり、コア臭がしないことが解るだろう。正直セールス、知名度は今一つであったものの、楽曲の完成度という意味では、ロックンロールでもハードロックでもない、誰もが思い描く“J-Rock/V-Rockらしさ”を象徴するような、BOØWY「MARIONETTE」、BUCK-TICK「惡の華」、LUNA SEA「ROSIER」に匹敵するほどのシーンを代表する楽曲だと思っている。
BUG「NEW WORLD」(2001年)
https://www.youtube.com/watch?v=Tfctw3BJW4Q
THE MAD CAPSULE MARKET’S、DIE IN CRIES、BLOODY IMITATION SOCIETY… など、ギタリスト・室姫深の音楽遍歴とシーンへの影響力は計り知れないが、J-Rock/V-Rockのヘヴィサウンドといった意味で、BUGをあげておきたい。ヘヴィサウンドながらも、歌がとことんメロディアスでポップだということもこのバンドの特徴である。
「キミの未来」と同様に先ず楽曲があり、ヘヴィ要素を足していった趣があるが、注目すべきは7弦ギターの使い方だ。ヘヴィロックという分野での7弦ギターではなく、ポップロックにおける7弦ギターの可能性を確立している。KORNの使用で一気に広まった7弦ギターだが、BUGの使い方は低音を主体とした7弦ではなく、ギターの弦が7本あることによるサウンドの厚みとでもいっておこうか。BUG曲は7弦開放(Low-B)の使用頻度が圧倒的に少ない。7弦開放で低音を主体とするよりも。7弦3フレットを押さえてDのコードに重厚さを与える使い方である。ギターを弾かない人に説明するのであれば、ギターは本来、弦が6本なので同時に鳴らせる音は最大6音である。だが、7弦ギターは通常より1弦多いので、同時に7音鳴らすことが出来る。それにより、コードのバリエーションや、サウンドに厚みが出るのである。「NEW WORLD」でも、イントロをはじめとする印象的なリフでしか、7弦開放のLow-Bは出てこない。
「昔はよかった」など言うつもりは毛頭なく、懐古に浸るわけではないのだが、やはり先人たちの残したものは偉大であり、後世に伝えていきたいものである。